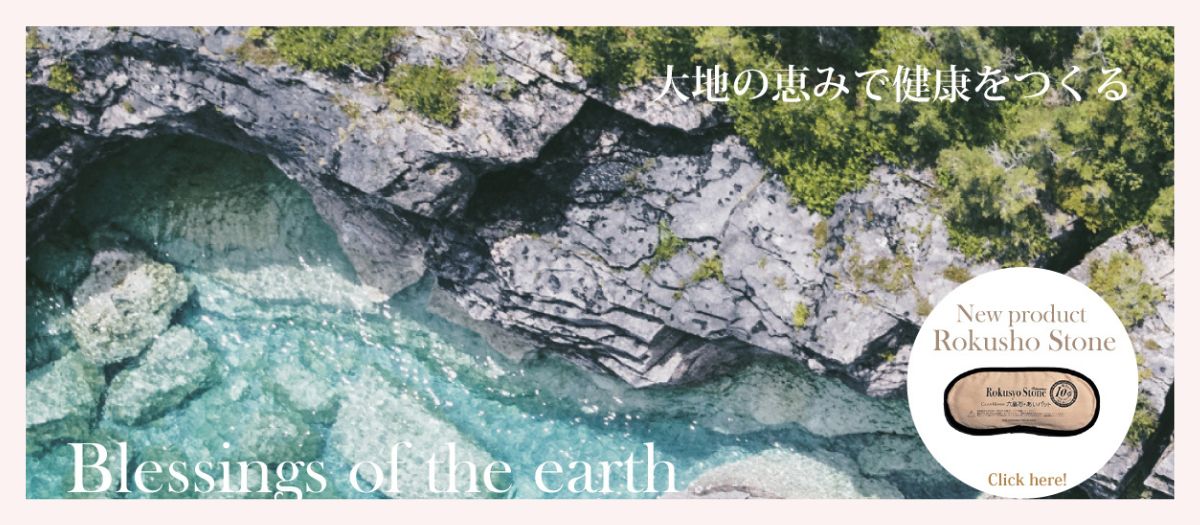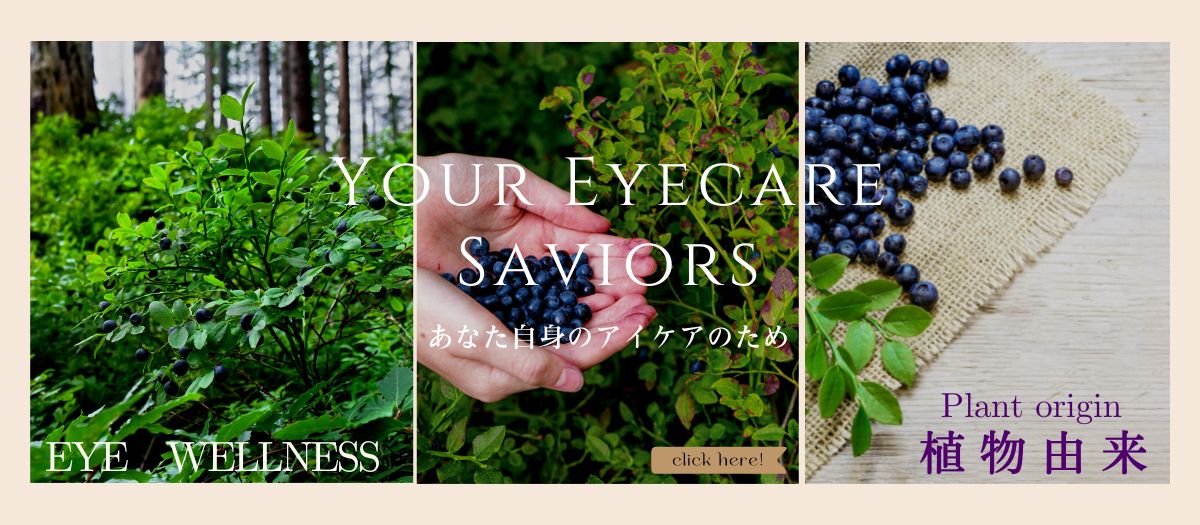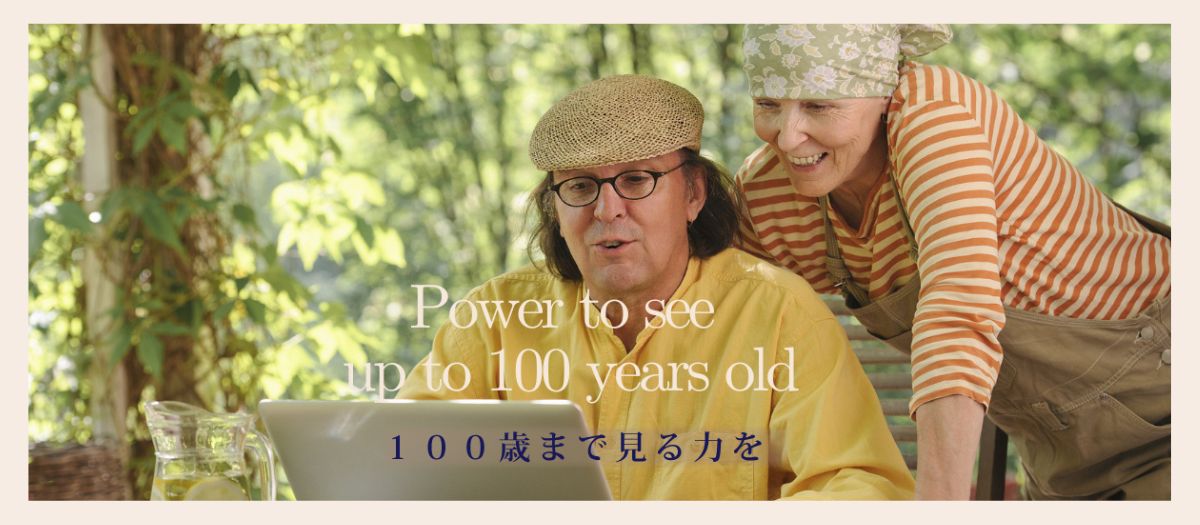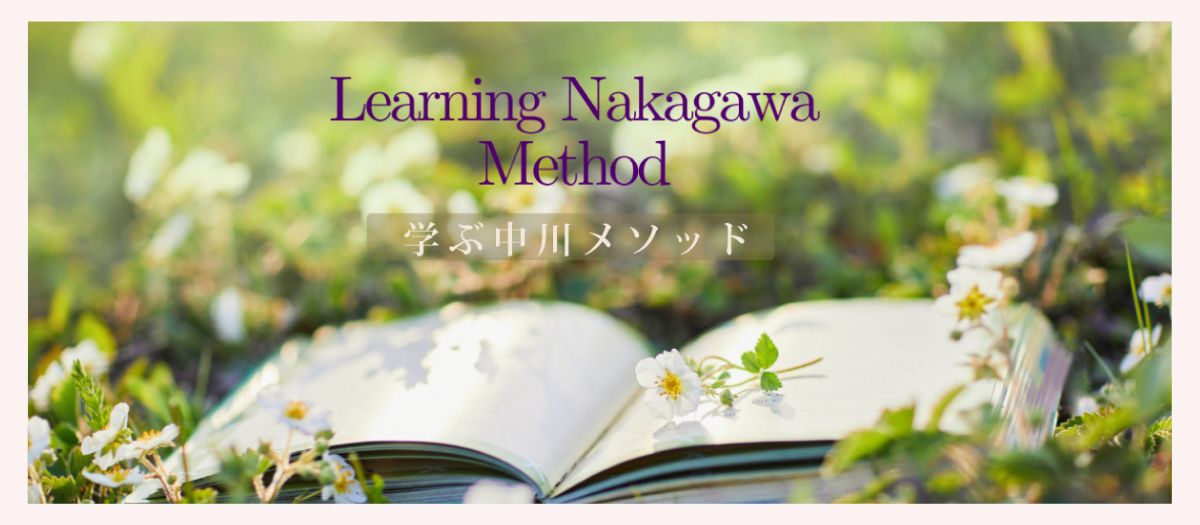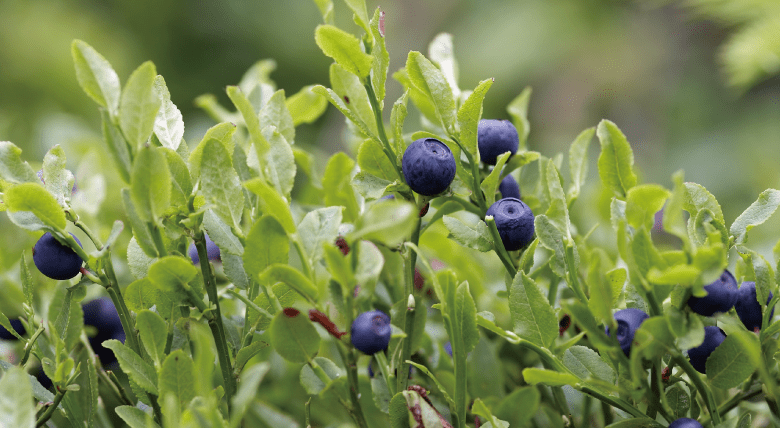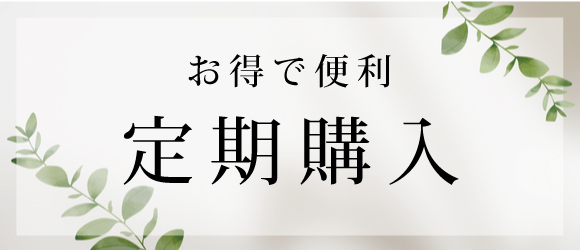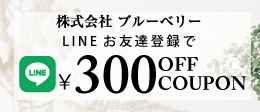ひとみ健康辞典
目のしくみと働きを知る
目は重要な情報収集器官
人間は情報の80~90%を目から得ています
人間は、視覚、臭覚、聴覚、味覚、触覚という五感を駆使して、生きるために必要なさまざまな情報を外界から得ています。
このうち80~90%は目を通して得る情報といわれており、目は情報収集力を身体の中で持っている1番重要な器官。それゆえ、常にハードに働き続けなければならず、さまざまな原因でものが見えづらくなると日常生活に大変な不便を強いられます。
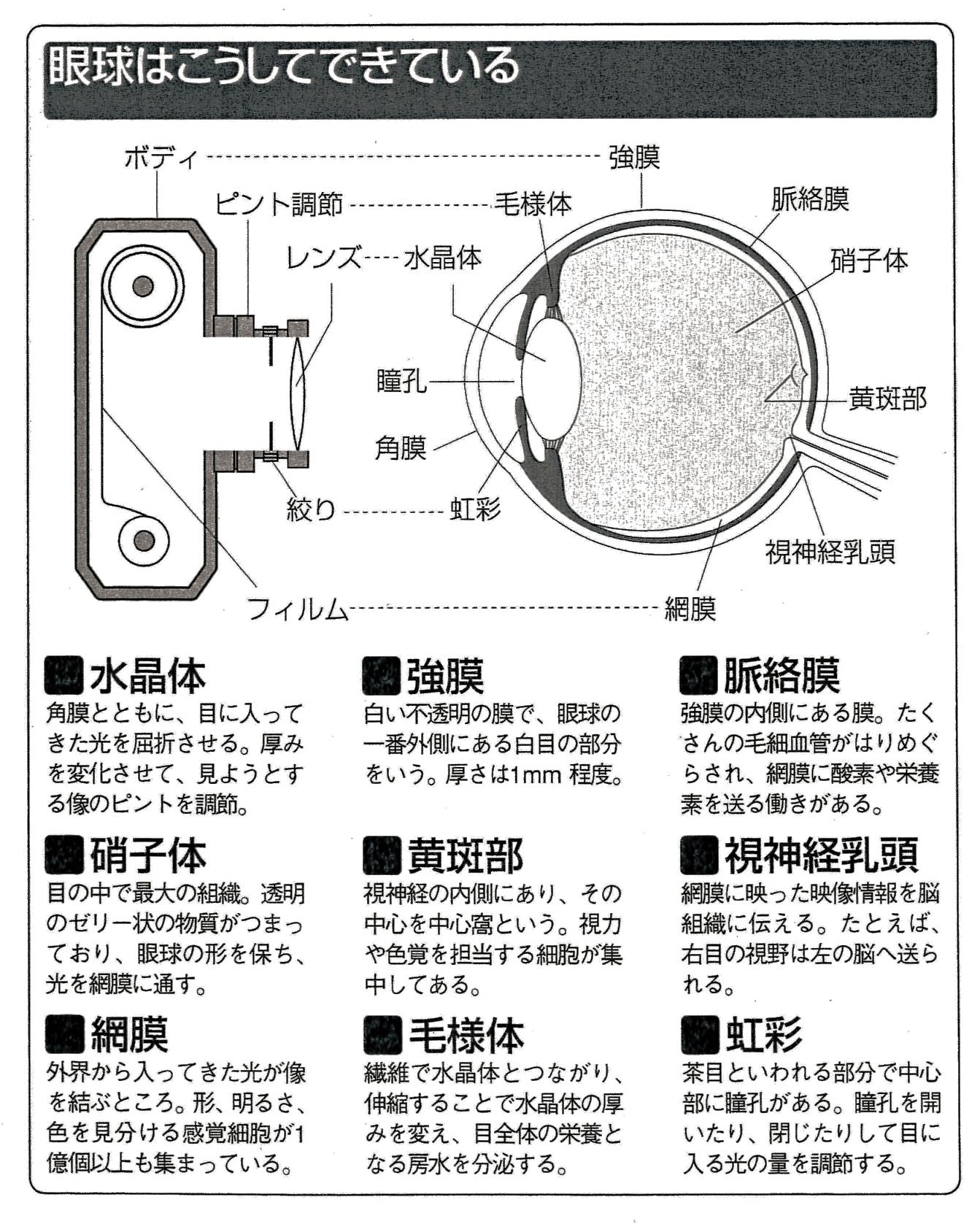
目の働きのことを視機能といいますが、視機能には視力、視野、色覚、光覚とい4つの働きがあります。視力とは、ものの形や存在を認識する目の能力のこと、視野は目を動かさないで見ることのできる範囲のことをいいます。そして、色を感じる能力を色覚、光を感じその強さを判別する能力が光覚です。それぞれどれも大切な機能ですが、ものを見るということからいえば、視力と視野は視機能の中でも特に重要です。
人間は両方の目を無意識に使ってものを見ていますが、両目で見ることでものが遠くにあるのか、近くにあるのかを判断したり、立体感覚を認識することができます。2つの目が必要な情報を過不足なく集め脳で判断して、正しく対象物を認識することができます。
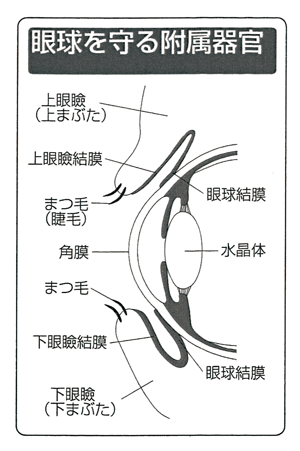
眼球、視神経、附属気から構成。
目の構造はカメラに似ています
一般に「目」と呼んでいる部分は具体的には、外界の光や形をとらえる「眼球」、視覚情報を脳に伝える「視神経」、まぶたやまつげや目を動かす筋肉など眼球の周囲にある「附属器」の3つにわけられます。眼球の内部にはものを見るための仕組みがあり、脳とつながっていて映像を伝える役目を担っています。ものを見るためのこれらの組織は、頭蓋骨の眼窩と呼ばれる骨のくぼみの中で保護されています。
眼球は成人の場合、直径が約24㎜、重さ7.5gのボールのような形をしています。目の構造はカメラによく似ており、水晶体と角膜はレンズ、虹彩は絞り、網膜はフィルム、眼球を取り囲む強膜はボディ、まぶたはレンズキャップに例えられます。外からの光は角膜を通って、主に水晶体で屈折しピントを合わせて網膜で像を結びます。その映像情報が視神経を通じて脳に伝わることで初めて見ることができます。
カメラと目の一番大きな違いは、目は厚みを自由に変えられる水晶体というレンズを持っているということ。カメラでは、レンズからフィルムまでの距離を調節してピントを合わせます。しかし目の場合、角膜(レンズ)から網膜(フィルム)までの距離はひとりひとり決まっていて変えることができないので、水晶体を薄くしたり、厚くしたりしてピントを調節しています。
目はこのように精巧なしくみを持っていますが、情報化された現代社会の自然環境や社会生活の変化は、目にも負担を与え、目にさまざまな弊害をもたらしています。一方、現代社会をとりまくさまざまな生活習慣病も、目の病気を引き起こす大きな原因となっています。身体と同じくらいに目の健康管理にも気を配りましょう。